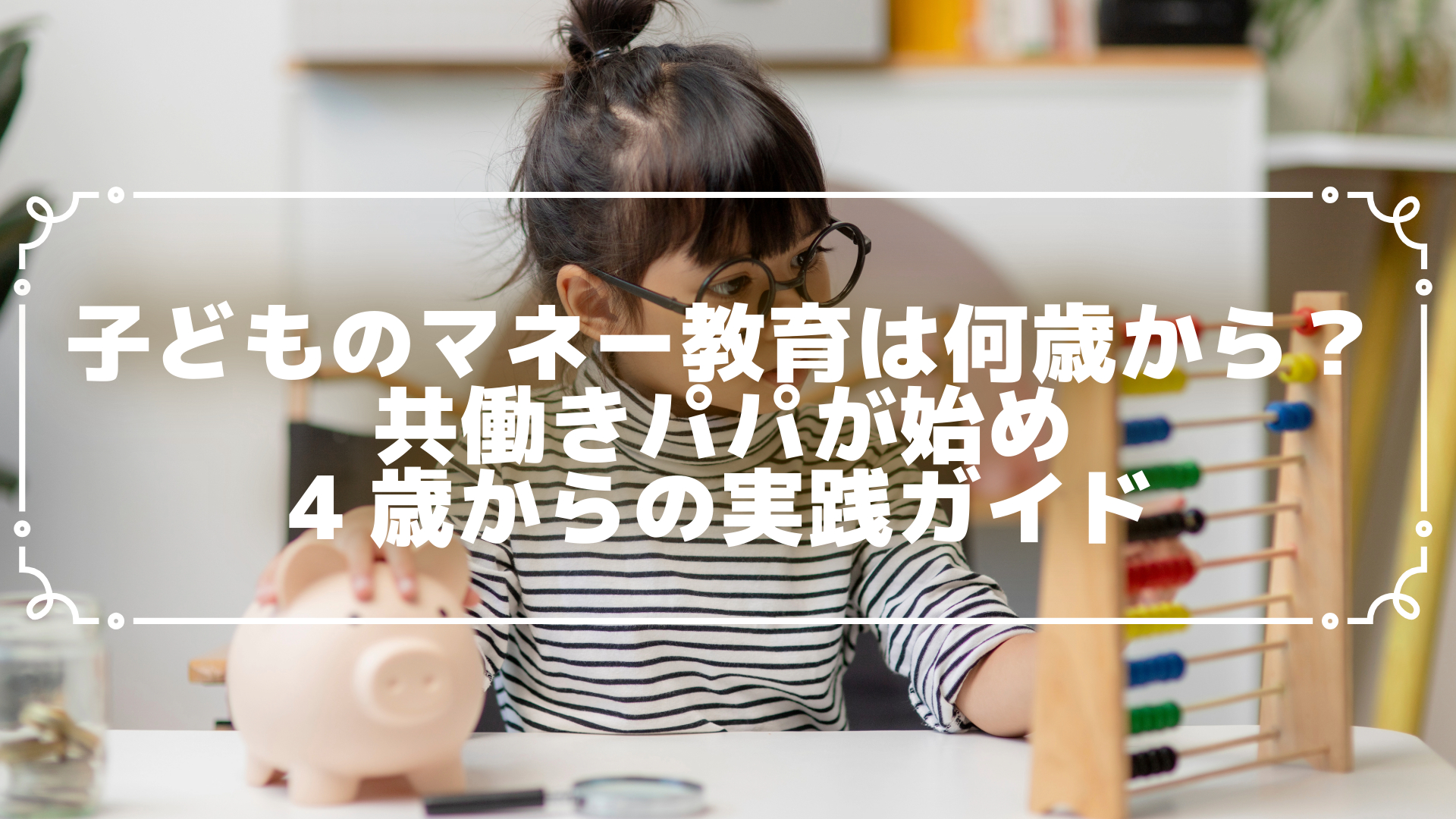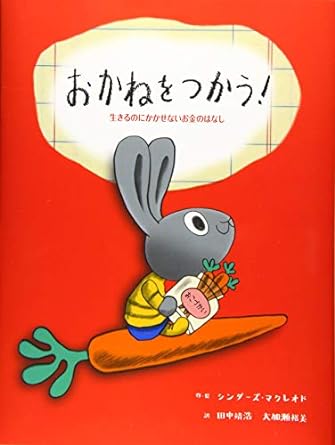マネー教育は早くてOK!4歳からでも始められる家庭での取り組み
「うちの子にも、ちゃんと“お金のこと”を教えなきゃな…」
共働きで4歳の息子を育てている僕も、そう感じ始めたのはつい最近のことでした。
キャッシュレスが進み、お金の「形」が見えづらくなった今、子どもに“金銭感覚”をどう教えるかは本当に悩ましいテーマです。
でも、実はマネー教育は、もっと気軽に、もっと小さなことから始められます。
この記事では、共働き家庭でも無理なく実践できる「幼児向けマネー教育」の始め方と、僕自身が実際にやってみて感じたことをお伝えします。
お金の教育は、3〜5歳からでも十分早くない
マネー教育と聞くと「小学生からじゃないの?」と思うかもしれません。
でも、発達心理学や脳科学の研究では、3〜5歳ですでに“お金=特別な力を持つもの”という感覚が育ち始めていることが示されています。
実際、Gasiorowska(2016年)の実験では、3〜6歳の子どもが“お金”に触れるだけで、他の子どもより自分で課題に取り組もうとする意欲(自律性)が高まり、同時に思いやり行動は減少したという結果が出ています。
つまり、お金は「道具」であると同時に、行動を変える“社会的刺激”でもあるということ。
数字が読めない年齢でも、子どもはすでに「お金には何か力がある」と相手の反応を見て分かっているのです。
この“敏感期”をうまく活かして、「使い方」「価値」「選択肢のある行動」を体験させることが、マネー教育の第一歩になります。
実際にやってみた!わが家のマネー教育ステップ
うちの息子が「それ、買って!」と毎回言うようになった3歳後半。
僕は妻と話し合って、マネー教育をゆるく始めることにしました。
実際にやってみたことは、こんな感じです:
① 一緒に買い物をする
まずは、スーパーで息子に100円を握らせて、好きなものを買わせるところから。
「どれにする?」「これはちょっと高いかもね」と話すことで、自然と“選ぶ力”も身につきます。
② お手伝いポイント制度
簡単なお手伝いをすると「1ポイント」もらえて、10ポイントで好きなお菓子を買える制度を導入。
この仕組みで「努力→ごほうび」という感覚が身についたのは大きな収穫でした。
③ パパと“お金の本”を一緒に読む
子ども向けの絵本『おかねをつかう! 生きるのにかかせないお金のはなし』などを一緒に読むと、「お金はパパが働いて得ているもの」と理解してくれるようになりました。
共働き家庭でも続けられる3つの工夫
「教えたいけど、時間がない」そんな悩みを抱える共働き家庭におすすめしたいのが、以下の工夫です。
- 週末だけ実践するルールを作る(土曜は“買い物体験の日”など)
- 生活習慣と組み合わせる(お風呂前にポイント計算)
- 子どもからの質問に「ちゃんと答える」ことを意識
特別な教材や高価な講座はいりません。家庭の中に“お金と向き合う瞬間”を少しずつ散りばめるだけでOKです。
やりすぎ注意!失敗から学んだ反省点
正直、僕も最初は少し張り切りすぎて失敗しました。
- 「これはムダ遣い!」と否定的な言葉ばかり使ってしまった
- ルールを細かく決めすぎて、子どもが混乱した
マネー教育は、「コントロール」ではなく「気づきのサポート」。
叱るよりも、一緒に考えるスタンスが一番です。
よくある質問(Q&A)
Q. お小遣いは何歳からがいい?
家庭によって違いますが、我が家は年中(4〜5歳)で100円を渡し、選ばせる練習から始めました。
Q. まだ数字が読めない子にはどう教える?
金額よりも「モノを手に入れるには価値が必要」と伝えるのが大事です。絵本や体験が効果的です。
まとめ|お金を通じて、親子の会話が生まれる
マネー教育は“早すぎる”ということはありません。
むしろ「お金は道具であり、使い方には考えが必要」と教えるのは、人生全体の土台になると感じています。
共働きで時間がなくても、100円と会話ひとつで始められるのが、マネー教育のいいところ。
今日のお買い物、ちょっとだけお子さんに選ばせてみてはいかがでしょうか?
参考文献
Gasiorowska, A., Chaplin, L. N., Zaleskiewicz, T., Wygrab, S., & Vohs, K. D. (2016).
Money Cues Increase Agency and Decrease Prosociality Among Children:
Early Signs of Market-Mode Behaviors. Psychological Science, 27(1), 1–14.
https://doi.org/10.1177/0956797615620378