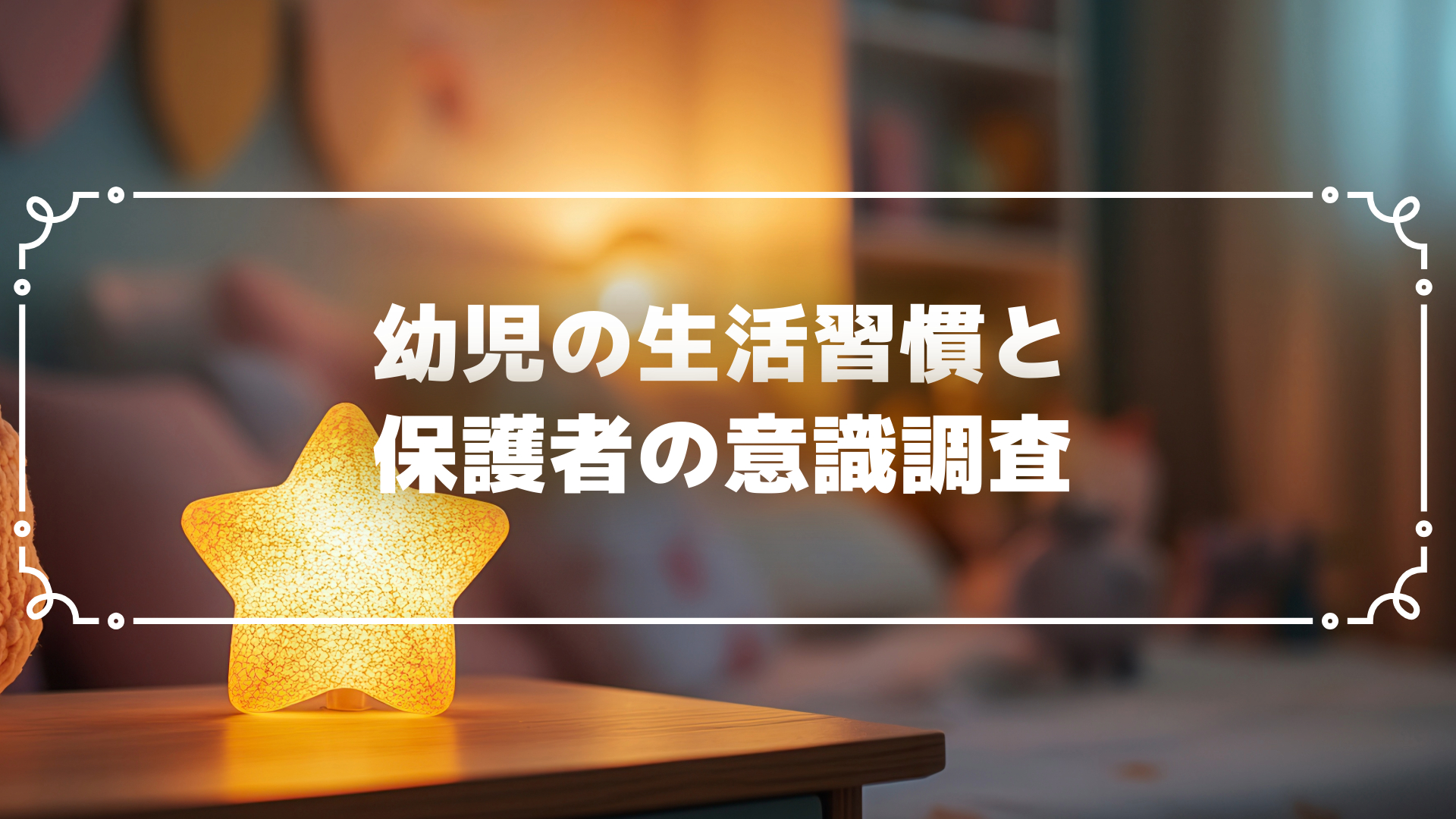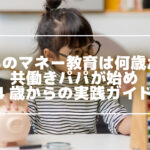幼児の生活習慣と保護者の意識調査から見える共働き家庭のリアル
「早寝早起き、ちゃんとできてるかな?」「スマホやテレビ、見せすぎかも…?」
子育て中の共働き家庭にとって、子どもの生活習慣は悩みのタネになりがちです。
僕自身、4歳の息子と毎日格闘しています。だからこそ、客観的なデータを通じて今の家庭の“ふつう”を知りたくなりました。
この記事では、ベネッセ教育総合研究所の調査をもとに、幼児の生活習慣に関するリアルな意識と、家庭でできる工夫を紹介します。
幼児の生活習慣で気になるトップ3
- 睡眠時間(夜更かし・起きられない)
- 食事の偏り(好き嫌い・朝食抜き)
- デジタル機器との付き合い方(スマホ・テレビ)
ベネッセ「幼児の生活アンケート」第6回(2022年)によると、夜9時以降に寝る幼児の割合は30%以上。
その背景には、親の帰宅時間や兄姉の生活リズムの影響もあるとされています。
加えて、コロナ禍を経て在宅ワークや生活スタイルが変わり、夜型のリズムが定着してしまったという声も増えています。
共働き家庭だからこそ、意識的に整えたい習慣
僕もそうですが、共働き家庭ではどうしても夜のリズムが遅くなりがち。
保育園のお迎えが18時過ぎ、お風呂と夕食であっという間に20時台。
そこから子どもが“自分の時間”として遊びたがるのは当然で、寝かしつけまで一苦労。
でも、意識して「ルール」を作ることで、子どもも安心して過ごせるようになります。
- 寝る前のルーティンを固定(お風呂→絵本→電気を消す)
- 朝食の“習慣化”のため、前夜に準備しておく
- デジタル機器の利用時間に上限を設定
我が家では「YouTubeは夜の自由時間に30分以内」とゆるくルールを決めて、なるべく時間を意識させるようにしています。
15分で終わる日もあれば、ぐずって延びる日も正直ありますが、「見すぎは疲れるからね」と一緒に振り返る時間をつくることで、少しずつコントロールできるようになってきました。
家庭でできる“ちょっとした習慣”が自立の第一歩に
ベネッセの調査では、生活習慣が整っている子どもほど「自分で着替える」「お手伝いをする」など、自立的な行動が増える傾向があると報告されています。
これは、生活の中で“やること”が明確であればあるほど、子どもは安心して「自分でやってみよう」と思えるからです。
うちでは、朝の準備を「息子専用チェックリスト」にして、毎朝一緒に確認するようにしました。
・顔を洗う
・パジャマを脱ぐ
・お着替えをする
・ごはんを食べる
これだけのことでも、「全部できた!」という実感がつくれるようになります。
“生活力”とは、小さな成功体験の積み重ねなんだと、最近よく感じます。
保護者の意識が変わると、子どもも変わる
ベネッセのアンケートでは、保護者の「しつけ」に対する意識も年々変化しています。
かつては「しっかり教えこむ」ことが重視されていましたが、今は「一緒に考える」「選ばせる」スタイルが増えています。
僕も以前は「早く寝なさい」「ダラダラしない!」と叱るばかりでした。
でも、最近は「どうすればスムーズに寝るか、作戦会議しようか」と話しかけるようにしています。
不思議とその方が、子ども自身も納得して行動してくれるんです。
まとめ|“うちだけ?”と思わずに、数字で安心しよう
「ちゃんと育てられてるのかな…?」と不安になることも多い育児。
でも、調査データを見ると「みんな同じように悩んでるんだ」とホッとできることもあります。
大切なのは完璧じゃなく、子どもに合った“日々の習慣”を見つけていくこと。
共働きパパとして、これからも試行錯誤しながら、家族でいいリズムを作っていきたいと思っています。
参考調査
ベネッセ教育総合研究所「第6回 幼児の生活アンケート」
https://benesse.jp/berd/jisedai/research/detail_5851.html